肛門は口から始まる消化管の出口にあたる部分です。大腸と肛門は切っても切れない関係にあります。大腸を診ないで肛門だけを診ることはできません。この理由から私たち中谷外科病院では”大腸肛門科”を標榜名にしています。
大腸肛門には様々な病気がみられますが、その中で痔(じ)は最も日常的で多くの人を悩ませている病気で、次の三つに分類されます。
1)痔核(じかく、いぼ痔)
2)裂肛(れっこう、切れ痔)
3)痔瘻(じろう、穴痔)
サルから進化したとされる人間は、四つ足から二本足で歩くようになり。大脳新皮質を発達させ、真善美の概念を持ち、人間社会を作り、痔に悩ませられるようになりました。
<痔の歴史>
人間と痔の関わり合いは古く、人類史の初期にまで遡ると推察されます。現存する文献を検索することで、人間が太古からどのように痔と関わってきたのかを知ることが出来ます。
キリスト教誕生よりはるか以前のBC400年ヨーロッパにはギリシャ文明が栄えていました。現在でも医師のモラルの最高の指針とされる有名な”ヒポクラテスの誓い”を著したヒポクラテスはこの時代の医師です。ヒポクラテスの残した医学書は医学史上最も初期の文献ですが、痔の診断と治療に関する記述が見られます。古代インド、中国の古い医学書にも紀元前から痔疾患に関する記載があります。

日本でも古代より肛門疾患の治療が行われていました。日本の痔の治療は552年、仏教伝来とともに中国から伝わったと考えられ、痔疾患に関する我が国最初の記載は718年、養老律令の注釈書”令義解”とされています。中世に至るまでの長い期間、病気は神のたたりと考えられ、治療は神にひたすら祈るという呪術によるものでした。鎌倉、安土桃山時代には痔の治療法として中国から伝わった腐食療法、結紮療法などが行われていましたが実際には呪術や経験による方法が主だったようです。
江戸時代には幕府が鎖国政策をとっていましたが、長崎にオランダ医学(蘭学)が導入されました。南蛮医学の渡来とともに日本における肛門疾患治療も変化し、呪術から脱した治療法が発達し始めます。近世と呼ばれるこの時代には杉田玄白(すぎたげんぱく)、本間棗軒(ほんまえっけん)など後世に名の残る医師が現れます。本間棗軒の著した”瘍科秘録”は現代でも学問的に高い評価をうける医学書で、肛門疾患の診断治療に関する詳細、具体的な記述が見られます。
明治時代に入ると、鎖国が解かれ、新政府より”西洋医術差し許し”の布告が発令されました。西洋分化がさかんに導入されるようになり、日本の医学にも大きな影響を与えました。ドイツ医学が主流となり、それまでの主流だった漢方医学はこの頃より衰退を始めます。
1945年の終戦と同時にアメリカ軍が日本国内に進駐し、マッカーサーら連合軍総司令部による統治下、日本の分化、政治経済はすっかりアメリカナイズされてしまいました。日本の医学会でも、この頃からドイツ医学が影を潜め、アメリカ医学一辺倒となっていきます。
アメリカの民主主義、科学万能手技、合理手技は多くの利益とともに様々な弊害を日本にもたらしました。一方、医学の分野ではアメリカが日本に貢献したことは否定できず、それまで不治の病とされていた病気や怪我に苦しんできた多くの日本の患者さんたちに福音をもたらしました。
<痔の治療法に対する考え方の変化>
1960年頃から肛門疾患の治療は根治を目的とするだけでなく、術後の肛門機能を重視した方法が重要であるという考えかたがひろがりました。私は1960年に生まれましたが、
例えば、痔の中でも一番患者さんの多い痔核の手術方法も変化しました。50年前は痔核にホワイトヘッド法という手術が行われていました。これは痔核を徹底的に全部切り取ってしまう手術法で、術後の激痛や肛門が狭くなったりする合併症が多く見られたことから次第に行われなくなりました。それにかわり、結紮切除術(けっさつせつじょじゅつ, L-E法)という手術法が痔核の標準的手術法となり、現在に至っています。最近ではレーザーなどの新しい機器が使用され、各施設で様々な工夫がこらされていますが、いずれも結紮切除法を基本としたものです。手術後の痛みが少なく、また手術の後の肛門の働きが良好なことから、当院ではアルゴンプラズマ凝固装置を使用して結紮切除術をおこなっています。
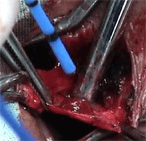

海外から多くを学んできた日本は今や様々な領域で、世界へ向かっての情報発信国となりました。現在日本で行われている大腸肛門病に関する研究や診断・治療法は世界に多大な影響を与えています。IT(Information
technology)化、グローバル化が進み、情報の国境がなくなりつつある現在、我々日本人は人類、そして地球人の一員として世界に貢献していかなければなりません。アメリカから導入された臓器別医療は現在日本にも広く浸透し、多くの優れた臓器別専門医を生み出しました。同時に、自分の専門外のことは全く解らないしまた興味もないというようないわゆる専門馬鹿も現れ、大きな社会問題となり、ライマリーケア(primary
health care)の重要性が見直されるようになりました。
抗生物質の乱用による薬剤耐性菌の出現、新たに出現したウイルスによる脅威など21世紀に生きる私たちには克服すべき新たな課題が与えられています。生殖、移植、癌末期の医療などに代表されるように、一歩間違えば、医療が持つ本来の使命が忘れられ、逆に生命の尊厳が損なわれかねない危険性のある現代、私たちはもう一度人間とは生命とはまた医療とは何かということを問われています。
私は日本大腸肛門病の専門医としての自覚を持ち、大腸肛門の病気に悩まされている人々に最善の治療法を提供し、大腸肛門の病気を予防するために努力していきます。
古今東西、老若男女を問わず、お尻の診察をうけることは羞恥心をともないます。中谷外科病院ではInformed consent(説明と同意)を大切にし、一人一人の患者様の気持に配慮し、誰もが安心して大腸肛門の診療を受けられるようスタッフ全員が努めています。
”恥ずかしさ”は受診を送らせる大きな要因です。
”気後れは後悔をもたらす。”というのは私の恩師である瀧上隆夫先生(チクバ外科胃腸科肛門科病院院長)の言葉ですが、私も全く同感です。
このホームページを訪れてくれたことで、大腸肛門病とその治療法に対する正しい理解を深めていただければと思います。
日本の大腸肛門治療のメッカといわれる社会保険中央病院のホームページhttp://www.coloproctologycenter.com/index.htmlに“痔のおはなし”あります。
大腸肛門診療の実際が詳しく分かりやすい内容で書かれていますのでご参照ください。
 平成16年4月 中谷外科病院 中谷 紳
平成16年4月 中谷外科病院 中谷 紳